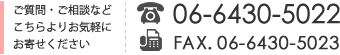段々と寒さが厳しくなってきましたね?
さてさて、10月のイベントで 尼崎大庄元気村で行われた
?衣川亮輔さんのミニミニコンサート? に行ってきました
マスク、手指消毒等の感染症対策をしっかり行い、
みんなで盛り上がりました(^▽^)/
最後に花束をお渡しし、記念撮影
皆さんいい笑顔~~!?
衣川亮輔さん楽しい時間をありがとうございました☆彡


皆様いかがお過ごしでしょうか?
暑い夏が過ぎ段々と季節が秋らしくなってきましたね
秋と言えば、、色々な秋がありますが
やっぱり食欲の秋!
秋の美味しい食べ物をたくさん食べて
エネルギーをもらい
赤チーム、メロディ全体で
日々の業務を頑張っていきます
朝晩の寒暖差が大きくなってきていますので
体調にお気をつけください
ホームページ編集係

今年に入り「新型コロナウイルス」の影響が各所に出ている中で
研修を実施する事が出来ず
「法令順守」の資料を配布し書面にて従業員全員に周知しました。
感染症対策を徹底し安全研修がに行えるよう
会議を重ねております。
次回研修は未定になっております
新着情報がわかりましたら随時更新してまいります
HP編集担当
先日弐番館で2名のご利用者様が99歳のお誕生日を迎えられ、
白寿のお祝いをさせていただきました。![]()
![]()
お二人仲良く記念写真を撮りました![]()
白寿は百から一を引くと「白」になることが由来だそうです。
怪我無くしっかり食べてお元気でお過ごしくださいませ![]()
改めましておめでとうございます!


メロディハウス・メロディハウス弐番館 ともに
適度な距離を保ち、ラジオ体操で身体を動かしていただいております![]()
体操をすることで、身体にも脳にも良い影響がたくさんあります![]()
自然と笑顔も増えますね![]()
「良い香りがするなぁ~」
「綺麗だなぁ~」
と、皆さま、いきいきと咲く綺麗なお花に、癒されていました♪
研修名 高齢者虐待
講師 大庄南地域包括支援センター 北村 茂樹氏
日時2019.6.19 メロディハウス2階
配布された高齢者虐待対応マニュアルと事例集を見ながら
高齢者虐待について学んだ。
1.高齢者虐待の定義
高齢者虐待防止法では「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています
また、高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待、②養介護施設従業者等による高齢者虐待
に分けて定義しています養護者による高齢者虐待とは養護者が養護する高齢者に対して
行う行為とされています。
(1)養護者による高齢者虐待
養護者とは、 高齢者を現に養護するものであって養介護施設従業者等以外のもの
とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます
養護者による高齢者虐待とは養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
①身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
(殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、身体拘束、抑制する
②介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による
虐待の放置など、養護を著しく怠ること
(例)入浴しておらず異臭がする。劣悪な環境で生活させる。
③心理的虐待
高齢者に著しい暴言又は著しく拒絶的対応その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)ののしる、屈辱を込めて子供のように扱う、無視する。
④性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者に対してわいせつな行為をさせること
(例)キス、性器への接触、セックスを強要する
⑤経済的虐待
養護者または高齢者の親族が該当高齢者の財産を不当に処分すること
その他高齢者の財産から不当に財産上の利益を得ること
(例)年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する
キーポイント
- 気づきの視点を身につける。虐待シート(尼崎市)を活用しましょう。
- 気づいたらまず相談を!1人で悩まず抱え込まないことが大切です。
- 虐待の可能性を意識しよう。
「高齢者虐待」は身近に起こりうる問題です。予防・防止していく為には
高齢者を取り巻く皆様の「気づき」が大切です


リスクマネージメントと対処法、高齢者の窒息
日時 2019/5/15
場所 メロディハウス2階 講師メロディナース 芝、白井氏
1転倒について
高齢者の方は転倒しやすく転倒したことがきっかけで寝たきりになることもある。
どうゆう方が転倒しやすいのか?
・特定の疾患を持ってる人・変形性膝関節症による膝の痛み
・心疾患による息切れ・食欲不振による低栄養状態
・目が見えにくい、耳が聞こえにくい・認知症、・骨粗鬆症
・薬を5種類以上飲んでる方4の割がふらつきや転倒しているデータがある。
・睡眠導入剤や精神安定剤を服用しているかたも注意が必要です
くすりによってふらつきがある場合主治医に薬の見直しをしてもらうのも対策の一つ。
転倒で一番心配なのは頭部の打撲です。
脳への衝撃は生命に関わることが多いのでぶつけたらなるべく早く受診すべきです。
転倒していた又はしてしまった場合は、すぐに起こすのではなくまずは冷静になって状況を
把握しどこに連絡するか判断することが大切です。
2窒息について
窒息を起こしやすい高齢者の特徴
・歯が衰えてきている・飲み込む力が弱い・噛む力が弱い・唾液の量が少ない
窒息しやすい食べ物は?
1食物(食品であるが詳細不明のもの)
2おかゆ類
3餅4ご飯5肉 (個人差によります)
万が一窒息が起きたらどうしたら?!
1大声を出す
2チョークサイン(窒息のサイン)の確認
3意識が無い→救急車を呼び心肺蘇生(AED)
4意識があり指示が伝わる人の場合は咳を促して喀出を試みる
5背部突き上げ方(ハイムリッヒ法)
6背部叩打法
※腹部突き上げ法の手順
1患者の後ろに回りウエスト付近に手を回します
2一方の手でへその位置を確認します
3もう一方の手で握りこぶしを作り親指側を患者の「へそ」の上方で
みぞおちより十分下方に当てます
4「へそ」を確認した手で握りこぶしを作りすばやく手前前方に向かって
圧迫するように突き上げます
5腹部突き上げ法を実施した場合は腹部の内臓を傷める可能性がある為
救急隊員に伝えるか、速やかに医師の診察を受けさせてください
※背部叩打法の手順
1患者の後ろから手のひらの基部で左右に肩甲骨の中間辺りを
力強く何度も叩きます。
※妊婦や乳児は腹部突き上げ法は行いません。背部叩打法のみ行います
研修名 法令遵守・個人情報保護研修
日時 2019/4/17
場所 メロディハウス2階 講師 松本ケアマネージャー
法令遵守と個人情報保護の研修を行いました。
個人情報の取り扱いやできること出来ない事を
参加者全員で再確認しました。
研修で学んだことを思いながら日々の
業務に取り組みたいと思います。
【研修名】腰痛にならない移乗の方法 【場所】メロディ弐番館
【講師】理学療法士 山中氏
【研修内容】
今回はプロジェクターを使用し、ユーチューブにて講義をしました。
①その先に必ず目的がある。その目的を達成させる為には身体介護が必要
②利用者自身の 出来る事 出来ない事 を見極める視点が重要
③身体介護の原則 ・介助者も色々な体格の人がいるので、同じ方法で介助しなくてよい。
・安全確保が大事 ポイントをしっかり押さえる
・介護前の声掛け 自信を持つこと
・自分の楽な方法でよい
④ボディメカニクスを利用する ・片足を移動させる方向に向け、足を広げ、腰を落とし
身体を密着させ、身体の正面で介助する。
(身体を捻らず、てこの原理を利用する。)
⑤車椅子からのベット移乗 ・ベットと車椅子の角度は45度
・ベッドの高さを少し低くする。
・利用者の身体を前屈気味にすることによって、体重を分散させる
⑥寝返り介助のコツ ・みぞおちの後ろと膝関節を持って体位変換をする
・片関節と股関節を持って体位変換をする
【研修成果と業務に生かすこと】
・基本のポイントを押さえ、方法は全員で統一するのではなく、自分の身体に合わせた方法を見つける
・確実で安全な介助が行える方法を選択する
【感想・備考】
身体を捻らない介助が身体を守る為にもこれから活用していきたいと思いました
安全確保をまず優先してそれぞれの介助方法が可能だとわかり、これからの業務に活かせると思いました